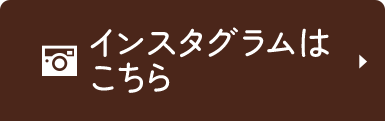納豆の効果がすごすぎる!血糖値・腸内環境に効く食べ合わせ5選

健康食として長年愛されている「納豆」。
「体にいいって聞くけど、何がどういいの?」「どのタイミングで食べたらいいの?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、医学的視点から、納豆の健康効果を分かりやすく解説します。
さらに、納豆の健康効果を最大限に引き出す「最強の食べ合わせ5選」も紹介していきます。
納豆の主な健康効果4選
1. 血糖値の上昇を抑える
納豆は血糖値の急上昇(血糖値スパイク)を防ぐのに役立つ食材です。
豊富な食物繊維が糖の吸収をゆるやかにし、特に「食前に納豆を食べることで食後血糖値の上昇が抑えられた」という研究データも報告されています。
さらに、納豆に含まれる「大豆タンパク」や「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」も、血糖値の急上昇をゆるやかにする働きがあると言われています。
-
納豆1パック(約50g)あたりの食物繊維量➡︎約2.2g
- このうち、
- ◼︎不溶性食物繊維 約1.6g …腸を刺激して排便を促す
- ◼︎水溶性食物繊維 約0.6g …糖や脂質の吸収をゆるやかにする
- 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用
2. コレステロールを下げる
納豆に含まれる食物繊維や植物性のたんぱく質は、体の中にたまった悪玉コレステロールや中性脂肪を外に出すサポートをしてくれます。
さらに注目したいのが、あの“ネバネバ”の正体。
納豆の粘りに含まれる「ムチン」という成分には、余分な脂質を包み込んで、体の外へ出してくれる働きがあるんです。
3. 血液をサラサラにする
納豆に含まれる酵素「ナットウキナーゼ」には、血栓(血のかたまり)を溶かす作用があるとされ、脳梗塞や心筋梗塞の予防にも注目されています。
糖尿病や脂質異常症によって血液がドロドロの状態になると、血管の壁が傷つきやすくなり、血栓症のリスクが高まる原因に。
納豆を日常的に取り入れることで、血流を促進し、動脈硬化の進行を抑えることが期待されています。
4. 骨を丈夫にする
納豆に含まれる「ビタミンK」には、カルシウムを骨に定着させ、骨粗しょう症の予防に役立つ効果があります。閉経後の女性においては、納豆を週6〜7回食べると骨折リスクを50%前後減らせるという研究報告もあります。
納豆を食べるなら朝?それとも夜?
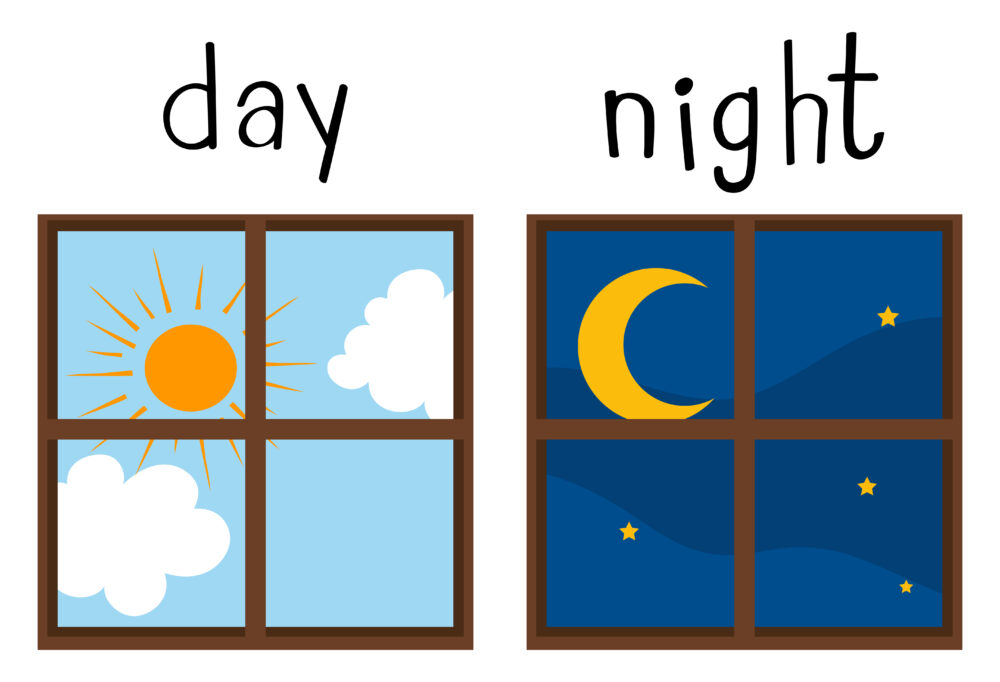
-
夜に食べるメリット
- 血液をサラサラ効果・血栓予防効果を重視するなら夜に食べるのがおすすめです。
-
血栓は朝から午前中にかけてできやすいため、血栓予防を意識するなら、夕食時に納豆を食べるのが理にかなっています
-
朝に食べるメリット
- 朝は腸が活動を始める時間帯なので、良質なタンパク質と納豆菌が腸の目覚めを助けてくれます。便秘気味の方や腸活を重視したい場合は朝に摂取するのがいいですね!
- さらに、体内時計をリセットして代謝を整えたい人、リズム食習慣を身につけたい人にも、朝の納豆ごはんはおすすめです。
納豆の効果を最大限引き出す!おすすめの組み合わせ5選
1. 納豆×キムチ
キムチ納豆は、コンビニでも売られている王道コンビ。
美味しいだけじゃなく、腸内環境を整えてくれるコンビなんです。
-
納豆菌 × 乳酸菌 ➡︎ 善玉菌がたっぷり!
-
大豆+白菜の食物繊維 ➡︎ 善玉菌のエサになる!
腸に「生きた菌」と「そのエサ」をいっしょに届けるイメージ。
腸活をしっかりしたい方におすすめです。
💡注意点
キムチは塩分が多いので、納豆に付属のタレは控えめにするのが◎
2. 納豆×オクラ・めかぶ・長芋
オクラ、めかぶ、長芋には、納豆と同じく「ムチン」という水溶性のネバネバ成分が含まれています。
- 💡ムチンのうれしい働き
-
◼︎糖の吸収をゆるやかにする
-
◼︎コレステロールを包み込んで排出
-
◼︎腸内のバリア機能を高める
納豆は不溶性食物繊維、オクラ・めかぶ・長芋は水溶性食物繊維が豊富。
このバランスがとてもよく、ズボラの方でもでも混ぜるだけなので簡単に取り入れることができます。
3. 納豆×玉ねぎ・ねぎ
納豆に玉ねぎやねぎをちょい足しするだけで、健康効果がぐんとアップします!
💡玉ねぎ・ねぎに含まれる成分
-
◼︎硫化アリル…血糖値の上昇をゆるやかにするはたらき
-
◼︎オリゴ糖…善玉菌のエサになって、腸内環境をサポート!
この2つの成分が、
✅ 血糖値スパイクの予防
✅ 腸活
の両方にアプローチしてくれるんです。
🧅 刻んで納豆に混ぜるだけ。
冷蔵庫に常備しやすい食材なので、手軽に取り入れられるのも嬉しいポイントです。
4. 納豆×しらす
しらすには、カルシウムとビタミンDがたっぷり。
納豆に含まれるビタミンKと一緒にとることで、骨を強くするはたらきが高まるといわれています。
💡こんな人におすすめ!
-
◼︎骨粗しょう症が気になる方
-
◼︎牛乳やチーズが苦手な方
-
◼︎閉経後の女性
さらにしらすは、塩分控えめでもうま味がしっかりしているので、
納豆のタレを使わなくてもおいしく食べられます。
5. 納豆×海苔(のり)
コンビニでもよく見かける「納豆巻き」。
実は、健康効果の面でもかなり理にかなっている組み合わせなんです!
◼︎のり…水溶性食物繊維が含まれていて、腸内環境を整えるサポートに。
◼︎酢飯…お酢には、血糖値の上昇(スパイク)をゆるやかにするはたらきがあります。ただし、酢飯にはお砂糖も含まれているので注意。
◼︎冷たい状態…納豆の酵素「ナットウキナーゼ」は熱に弱いのですが、冷たいまま食べる納豆巻きなら、酵素のパワーを保ったまま摂取できます!
実は合わない人もいる?注意すべきケース

ワーファリン服用中の方は要注意
納豆には「ビタミンK」という成分が多く含まれています。
このビタミンKには、血液を固める(凝固させる)作用があるため、血液をサラサラにする薬(ワーファリンなど)を服用している方は注意が必要です。
ワーファリンは、血栓(血のかたまり)ができるのを防ぐお薬ですが、ビタミンKを多くとると薬の効き目が弱くなってしまうことがあります。
そのため、納豆を食べることで薬の効果に影響が出てしまう可能性があるのです。
もし、ワーファリンなどの抗凝固薬を処方されている場合は、
納豆を食べてもよいかどうか、必ず主治医や薬剤師に相談しましょう。
SIBO(小腸内細菌異常増殖)やFODMAP過敏症の方
納豆は基本的に体に良い食品ですが、体質によってはお腹の不調を感じることもあります。
たとえば、
-
◼︎SIBO(小腸内細菌異常増殖)の方は、発酵食品でガスや膨満感が出やすくなります。
-
◼︎FODMAP過敏症の方も、納豆に含まれる成分でお腹が張ることがあります。
「納豆を食べるとお腹が苦しくなる」「ガスがたまりやすい」など心当たりのある方は、無理に食べず、医師や管理栄養士に相談してみてくださいね。
ちなみに、
SIBOやFODMAPの可能性が気になる方は、
👉 公式LINEに「フォドマップ」と送ると、「FODMAP食一覧」を無料でプレゼント中です!
まとめ
納豆には、血糖値・コレステロール・血液・骨といった生活習慣病予防にうれしい効果が詰まっています。
さらに、キムチやオクラ、シラスなどの食材と組み合わせることで、より効果的に体を整えることができます。
ただし、体質に合わない方もいるため、無理せず「自分に合う範囲」で取り入れることが大切です。
納豆、あなたの食卓にぜひ取り入れてみてくださいね!
↓当院の受診予約はこちらから↓
↓お電話でのご予約希望の方はこちら↓